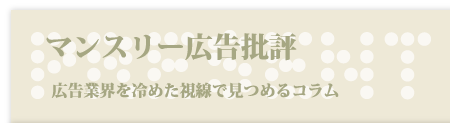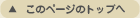1人のクリエイターによる真正面からの広告論、「広告の迷走」。現状を見渡す限り、それだけでも貴重な書籍 だ。著者・梶祐輔氏は、言わずとしれたコピーライター、いや広告界の大御所である。それは例えば歌舞伎界で言えば生前の六代目・中村歌右衛門、俳優業界の 森繁久弥、落語界なら先頃没した五代目・柳家小さんとも称すべき正に重鎮。実際、私ごとき(落語界で言えば座布団運びの前座以前であろう)が取り上げるな ど正に身の程知らず以外の何物でもないのだが、そこは氏の手がけた広告そのものにではなく、あくまで氏の“評論”に対する“批評”ということでお許し頂き たい。これまでいくつかのメディアに社会・映画評論を(プロとして)発表し、現在も「URL TODAY」なるWebサイトに毎週、社会批評のコラムを執筆している私は、少なくとも評論家としての一般大衆の知名度という点では、殆ど梶氏と同じ程度 に低いと捉えてよいと思う。 「広告の迷走」と謳うからには、“迷走する広告”に対する苦言が並んでいるのは言うまでもない。初めに申し上げるが、私は氏の指摘する苦言に納得した点は 多い。と言うよりも、(1)日本のテレビCMは「タレント依存症」になっている(2)メディアミックスの表現がすべてテレビCMに準じている(3)その CMの表現はライト・ユーザー=「価格で動き、移り気で、ブランドとは縁がない」向けにシフトしている(4)「地球にやさしい」の氾濫(5)「商品に差は ない」という広告の作り手の論調に対する問題提起等は概ね広告関係者の常識であり、論じられすぎて手垢がついた感さえあるほどだ。本欄の批評の指摘がほぼ 前半部に偏っているのは、その意味で後半に興味が湧かなかったからである。 私が指摘したかったのは、そのようなマジョリテイとしての正論ではない。
プロモーションへの自意識過剰。
本書の冒頭、梶氏は「広告を『商品を売るためのコミュニケーション活動』と考えるその常識、憲法が間違いだったとすれば、どうなるのだろうか。」と疑問提 起し、広告を「消費者やスティクホルダーとの『信頼関係をつくるもの』なのである。」(「スティク」は原文のママ)と定義し、疑問提起したその章の終わり を次の言葉で結んでいる。「この話はもうやめよう。アドバタイジングは、『商品を売る』ことを止める。それはプロモーションが本来の役割に立ち戻って頑張 ることにつながるということを、ぼくはいいたかっただけなのである。」
言うまでもなく(株)電通が毎年発表している「日本の広告費」にはプロモーションの売上が含まれている。だから梶氏の指摘が誤りと言うのではもちろんない が、少なくとも消費者はアドバタイジングとプロモーションを同じ広告として捉えていることは容易に想像がつくし、そもそも「アドバタイジングは『商品を売 る』ことを止める」という提案が、アドバタイジングそのものの表現や機能を狭める結果をもたらすことを私は危惧する。広告の目的を各自が定義することは自 由だし、広告の存在そのものをテーマとした議論は、日々流され、あるいは抗しながら広告制作しているクリエイターたちにとって有意義な機会を提供すること は間違いない。しかし過度にプロモーションを意識し、アドバタイジングの範囲を狭め必要以上に保護しようとする梶氏の意図は様々な点で矛盾と差別を呈せざ るを得ない。そして、その意識の奥に私は氏のプロモーションに対する差別意識を見るのである。
矛盾の(1)梶氏は本書29ページで最初に広告を「消費者やスティクホルダーとの信頼関係をつくるもの」と定義し「アドバタイジングを『商品を売ること』 から解放すること。アドバタイジングは『商品を売らない』と決めること。」と主題を述べている。しかし、いま各企業はコーポレートブランドを創りあげると いう大きな目的の中でプロモーションも広告と同じ位置づけで捉えているし、別の表現で言えばプロモーションは消費者やステイクホルダーとの信頼関係をつく るものの一つになりつつあると言える。例えば日本経済新聞(02年4月17日)は「日産自動車は販売会社の店舗や広告などのイメージを世界的に統一する新 しいブランド戦略を展開する。(中略)対象は店舗設計やテレビコマーシャル、インターネットのWebサイトなど消費者との接点になる部分すべて。」と報じ ている。この日産の「新しいブランド戦略」はアドバタイジングとプロモーションを全く区別していない。よって、前述の氏の定義は確かにアドバタイジングの 定義にはなり得るかもしれないが、だからと言ってプロモーションを除外することはできず、不完全である。
矛盾(2)梶氏は本書29〜30ページでアドバタイジングとプロモーションの差異を自ら整理しており、その中でアドバタイジングの目的を「マインド・シェ ア(消費者の意識における企業の優位性=川中注)を高めること」、プロモーションの目的を「マーケット・シェアを高めること」としているが、この定義で個 々の広告や販売促進ツールを明確に振り分けるのも現実的に不可能である。例えば店頭POPは梶氏の意識の中では当然プロモーションに属するであろうが、 スーパーの食品売場の店頭で「無添加・無着色」をアピールすることは、商品特徴の訴求と共にそうした方針で食品製造に取り組む企業姿勢も同時に訴求するも ので、少なくとも消費者の信頼関係づくりには貢献していると思われる。つまり消費者(もしくはステイクホルダー)の信頼関係づくりに通じるプロモーション も成立し得るのである。アドバタイジングとプロモーションの差異をマインドとマーケットという基準を用いて無理やり作りあげようする意図は、この事例以外 に数多くの矛盾を生むに違いない。「マインド・シェアを高めること」を目指したプロモーションは、数多く存在するに違いないからである。
矛盾(3)(2)で述べた整理の中で梶氏は、アドバタイジングを「長期にわたって商品が売れつづけるために絶対不可欠な信頼関係をつくるコミュニケーショ ン活動」、プロモーションを「目先の商品を売り切るための各種の販売促進活動」としている。穿った見方かもしれぬが、この「目先の商品を売り切る」という 表現は明らかに差別の感情を含んでいる。「販売上の重点商品の売上を向上させるための各種販売活動」でなぜいけない。この方がよほど正確である。「販売上 の重点商品」は季節や他商品との兼ね合いで随時変わる。別にことさら「目先の」などと蔑まなくても(「目先の」自体にそうした意味のないことは承知だが、 この文脈では差別の意味合いが濃いと言っている)事は足りる。仮に「目先の」を活かしたとしても「商品を売り切る」という表現は曖昧である。「目先の販売 計画数を売り切る」がより適切であろう。これらは何も“重箱の隅をつつく”式の悪意に満ちた指摘ではない。評論とはそもそもそうした論理的な整合性がなく てはならぬと言いたいのである。
「長期にわたって商品が売れつづける」と「目先の商品を売り切る」も実に曖昧で分かりづらい表現である。ここで述べている「長期」とは一体どの程度の期間 を指すのか? 「目先」とはどの程度、短期間なのか? 実はこの点は本書33ページで「プロモーションが、一ヶ月ごと・四半期ごと・一期ごとに目標を掲げ、結果を評価するとは、根本的に異質のものなのだ。目先 の『商品を売る』プロモーションと、お客の心とのあいだに長期にわたる『絶対の信頼関係をつくる』広告とが、絶妙のバランスを保って展開されるとき、企業 は厳しい国際競争を勝ち抜いて生き残るだろう。」(「評価するとは」は原文のママ)と述べているのだが、ここでも「長期」がどの程度の期間かは示されてい ない。
広告戦略上、“長期にわたる広告”とはキャンペーンを指すものと一般的にはとれるが、それなら例えばアサヒビールが行っている販売促進が主目的と思われる ビールの“広告”(氏の定義では広告に入らないようなので“”で括る)のように、“長期にわたる売り上げ拡大”を目指したキャンペーンはどちらに入るの か? 決して「目先の商品を売る」目的ではないが明らかに販促に重点を置いた同社の一連の“広告”は少なくとも目先と長期で分ける氏の期間による基準では区別す ることができない。恐らく梶氏は、このアサヒの“広告”に限らず、目先の商品を売り切ることが目的ではなくしかも長期に渡る“広告”のうち、表現上販促の 色彩が強い“広告”の類を広告とは認めたくないのであろう。また、その類の“広告”は「絶対の信頼関係をつくる」広告ではないと言いたいのであろうが、こ の点については後ほど詳しく述べることにする。
以上指摘した3つの矛盾は、メディアで区切る以外そもそも境界線の曖昧な部分が多いアドバタイジングとプロモーションをいとも簡単に整理しようと試みた結 果であり、あまりにもほころびが大き過ぎる論理展開は、評論としては不用意と言ってしかるべきである。
プロモーションへの差別意識。
さて、梶祐輔氏はなぜこのような粗雑な定義までして広告を、商品を売るためのコミュニケーション活動から切り離そうと試みたのか? 私はそこに梶氏のプロ モーションに対する差別意識を感じる。私が次に指摘したいのがこの点である。
梶氏は43ページで「この国の総合広告会社は、例外なくセールス・プロモーション部門をもっており、何人かのSPの専門家と称する手合いをかかえている。 しかしぼくはそこで、理論で磨かれ、実戦で鍛えられ、独自のノーハウを身につけて、しかも『商品を売ることなら任せなさい』という気構えに溢れた人物に 会ったためしがない。ほとんどの広告会社には、ほんとうの意味での販売促進のプロフェッショナルがいないのである。」と述べている。
先に私は「目先」という言葉に梶氏のプロモーションに対する差別意識を指摘したが、ここでは最初に「手合い」なる言葉を指摘したい。新明解国語辞典(第三 版)によれば、手合いとは「十ぱ一からげにされる程度のもの。」を意味する。もちろんここでは否定的な文脈の中で使われているが、現在活動するSP(セー ルス・プロモーション=川中注)の専門家を安易に蔑んだ表現で、「じゃあ、広告の専門家はどうなんだ!」と私は言いたくなる。 少なくともバランス感覚を欠いた記述で、これが差別意識の1点目である。
さて、もちろんコピーライターとして(コピーライター以外の分野もこなしているので)販売促進を仕事の一部としている私も、梶氏の表現を鑑みれば「販売促 進のプロフェッショナル」とは言い難い、と正直に申し上げる。しかし、私が言いたいのは、なぜ販売促進を仕事とする者を「販売促進のプロフェッショナル」 などという異端めいた存在に押しやるのか? ということだ。大手広告代理店(「広告会社」とは言いたくありません。いかにそれが広告マスコミの論調だとしても少なくとも現状から言えば)のコピーライ ターの皆様方なら「手間がかかるだけで面白くないSPは外注して広告だけやろう」で済ませることができるであろう(もちろんそれが不可能な場合もある) が、独立して営業を続ける多くの広告制作者たちは“広告もやれば販売促進もやる”という姿勢でないと暮らしてはいけない。したがって、氏からは恐らくそう 見えるであろう“販売促進だけやっているような”制作者も、どこかで同時に広告も制作しているのが実情なのである。
それでは「理論で磨かれ、実戦で鍛えられ、独自のノーハウを身につけて、しかも『商品を売ることなら任せなさい』という気構えに溢れた人物」という表現を 梶氏の言うところの“アドバタイジング”に置き換えたらどうなるであろう。「理論で磨かれ、実戦で鍛えられ、独自のノーハウを身につけて、しかも」まで は、職人やプロスポーツ選手にも通用するごく一般的な表現に過ぎない。では次の『 』の中に氏ならどんな言葉を入れるだろうか。本書で述べられている氏の言葉を用いるなら『その会社がどういう熱い想いをこめて会社をやっているのか、とい うことを伝えるのなら任せなさい』となろう。氏は本書38〜40ページで「広告を『経営戦略の一環』としてとらえるという発想なんぞは、まったく思慮の外 に置かれている」と述べ「広告にとっていちばん重要なのは『トップの指示』ではなく、いつの時代にも、広告のなかにほとばしる『企業トップの熱い想い』で はないかと考えている」と説いているからである。しかし、後述するように、この定義をもってしても広告をプロモーシ ョンと差別することはできないのだが、本書では「販売促進のプロフェッショナル」 については多くを割いているにも拘わらず、広告及びアドバタイジングのプロフェッ ショナルについての記述が皆無なので致し方ないのである。なぜ広告のプロフェッ ショナルについての記述がないのかは次項で述べるが、プロモーション (およびその 分野に従事する人間)の質を明らかに問題視する一方で、広告自身の質にまったく言及しない本書に、何らかの差別を感じることが不自然だとは思えない。これ が差別意識の2点 目である。
さてプロモーションへの差別意識の3点目として挙げたいのは冒頭で引用したように、広告代理店の機構を例に出して“広告を作る側”と“プロモーションを作 る側”を分けた点である。多くの広告制作者がその両方の側に位置するにも拘わらずである。氏はここで「セールスプロモーション部門に(中略)販売促進のプ ロフェッショナルがいない」とはっきりと述べているが、氏の指摘するように販売促進を目的としたテレビCMの作り手たち(大手広告代理店もしくは大手CM 制作会社のCM制作者)も同様に(氏の定義するところの)広告を制作しているはずだ。それなのになぜセールスプロモーションを「セールスプロモーション部 門」などという例を取り上げてまで、専門の作り手がやるものだと決めつけるのか? そして、“広告”の出番がなくなったテレビCMの現状を「もしセールスプロモーションが『商品を売る』べくほんとうに機能してくれたら、いまの不況は、 もっと早く解決したのではないか」(本書50ページ)などと、消費者の購買意欲の減退の原因を一方的にセールスプロモーションだけに押しつけるのか?これ らの見解は、論理的に見て全くバランス感覚を欠いており、私にはこうした見解が“広告を作れない一クリエイターの単なる欲求不満”として映るのである。そ して私はここに氏の“セールスプロモーションは、セールスプロモーションだけやっている人間にまかせておけばいい”という差別意識を見るのである。さらに 言うならば、「商品を売ることなら任せなさい」と表現し、明らかに数字で結果の出る現実の場にプロモーションを追いやっておきながら、広告に関しては「熱 い想いを伝える」という極めて曖昧な定義で済ませている点も一般人の広告に対する見地からは理解できないものである。しかし、本書にはそうした疑問に応え る文章も皆無なのである。
“鑑賞に値する”という広告の基準。
梶氏はカンヌ国際広告祭でグランプリを受賞した日清食品のカップヌードルのCM「ハングリー」を「この国ではまことに数少ない、アドバタイジングと呼んで いい」と賞賛している。もちろん私もあのカップヌードルのCMは傑作だと思うし、正にあれこそが広告といってしかるべきだと無条件で納得する。しかし、本 CMに対する賞賛と氏のアドバタイジングの定義を見比べると事情は異なってくる。果たしてあのCMシリーズは何年続いたろうか?「お客の心とのあいだに長 期にわたる絶対の信頼関係をつくる」という意味で果たして広告であったのか? という疑問がまず生じるのである。つまり、氏はいろいろと“広告”の定義を並べてはいるが、ここでも自らの定義に自ら矛盾を晒しており、結局は広告を単に “カンヌで賞を取れるような表現として高品質の作品”として考えたいだけではないのかという疑問が最後に残ってしまうのである。
なぜなら、このカップヌードルのCMを持ち出すまでもなく、結局は不完全にしか区別できなかったアドバタイジングとプロモーションの定義は、表現上の品質 のレベルを持ち出すことによって解決するからである。この概念については、本書61ページで印刷媒体に対する記述として明快に述べられている。「広告だか らといってポイと投げ捨ててしまうには惜しい、じっくり読んだり、鑑賞したりするに価する広告」という新聞広告に対する文章がそれである。梶氏はここ で、(同じビール工場で祖父・父・子に親子三代でビール醸造に関わってきた一族を紹介する)朝日麦酒の広告や松下電器の60年代前後の新聞広告を紹介し、 「いうまでもなく、このときわが国の広告は、全体としては『商品を売るためのコミュニケーション』路線をひた走っていた。けれども、どうしてもそういう 『売らんかな』の枠からはみ出してしまう一群の新聞広告があったのだ。」と記している。 つまりここで「商品を売るためのコミュニケーション=プロモーション」に対峙する概念としてはっきりと「じっくり読んだり(これはCMなら「観たり」とな ろう)、鑑賞したりするに価する広告」という表現を使っているのだ。そして、この「鑑賞」という意味で言うなら、「ハングリー」も当時の視聴者たちは確か に楽しんで「鑑賞」していたと言ってよいと思う。個々の広告表現を提示して氏が述べているこの“鑑賞するに値する”という広告の基準こそ、梶氏が明確に基 準と述べていないにも関わらず、唯一明確な広告の基準として成立している、と私は主張したい。また前述の文章から、氏もそれを意図していることは明らかで ある。
“鑑賞するに値する”なる定義が、広告の基準として成立するには次のような背景もある。商品やキャンペーンの内容を魅力的に伝えるという目的の下で行われ るプロモーション関連の制作物が“鑑賞するに値する”という基準をクリアすることは出発点からして決定的なハンデがあるという点だ。広告関係者以外の読者 に対してあえて書けば、プロモーション関連の制作物は、主としてリーフレット・パンフレット・ダイレクトメール・店頭ポスター、最近で言えばWebサイト などのメディアを対象に作成され、主たる目的として商品特性のストレートな伝達や消費者キャンペーン等のプレミアム情報の告知が最優先され、その他に企業 の姿勢などいわゆる「熱い想いを伝える」スペースを考えることは基本的に困難だからである(ではプロモーションには情報告知以外の機能はないのかと言えば 違うのだが、論旨から外れるのでここではその点にまでは言及しない)。
「販売促進のプロフェッショナル」などと販促の専門家の存在をことさら強調して論理を展開した裏に、プロモーションの言ってみれば独壇場である一連の販促 関連のメディアの存在があったことは想像に難くない。そして、そんな氏にしてみれば広告制作費が最も高価な(つまりクリエイターの技量が最も発揮できる) テレビCMであるにも拘わらず、プロモーションを目的とした表現が販売促進関連のメディアの領域を越えて氾濫しているのを許せなかったのである。そう考え れば氏が必死に整理したアドバタイジングとプロモーションの定義が結局は矛盾に満ちたものであったという事実も少しは納得できるではないか。
さて、私はここで再び梶氏の言う「販売促進のプロフェッショナル」という言い方に戻りたい。ある広告(としよう)が、「鑑賞するに値する」かどうかは、絶 対的に個人の主観に左右されるという事実がある。したがって、ある広告制作者が販売促進でなく「広告のプロフェッショナル」であるかどうかは、実は誰も決 められないのだ。ある広告を優れていると判断する一方で、「そんな広告よく分からない」と判断する層は必ず存在するからである。そして、だからこそ広告業 界は、数々の広告賞を通じて内輪の審査員の判断を広告のプロの判断として権威化し、広告賞が選定した広告に「鑑賞するに値する」という称号を与えてきたと 言ってよいのではないか(いくつかの広告賞にはそれ以外の判断基準で選ばれるものももちろんあるが)。したがって本書におけるプロモーションへの差別意識 は、広告賞を背景とする広告業界のコンサバティブな論理から発していると言ってよいと私は思う。
しかし、この賞を取る取らないの事実を除いた時、前述の「その会社がどういう熱い想いをこめて会社をやっているのか、ということを伝えるのなら任せなさ い」という広告のプロの定義の何と心許ないことか。売上高・販売数量という明白なる客観的な数字を判断基準に、それが実現されていないという理由でプロ モーションの制作者を(広告がプロモーション化している)犯人に仕立てておいて、明らかに矛盾に満ちたしかも曖昧なる定義を基に囲い込んだ“広告”の制作 者に何ら責任を負わせることなく、単に主観的に過ぎない表現レベルの品質及びそうした表現への制作者としての欲求を守ろうとした本書は、批評としての配慮 に欠けていると言わざるを得ない。
「熱い想い」における梶祐輔氏の矛盾。
5月19日の朝日新聞朝刊にアサヒビールの広告(“次のアサヒ”への決意です?新しいうまさへの挑戦)が掲載されている。これこそ私が前述した「アサヒ ビールが行っている販売促進が主目的と思われるビールの“広告”」である。キャッチフレーズは「すべては、お客様の『うまい!』のために。」キリンビール を抜いてビール・発泡酒シェアでトップに立つ同社の、これは「うまいビールをつくるための製造の姿勢」を示す企業活動を表現した“長期”キャンペーン広告 である。あえて「広告」と断ったのは、このアサヒの広告が梶氏の指摘する広告の定義である「その会社がどういう熱い想いをこめて会社をやっているのか」と いうメッセージそのものだからである。本広告に限らずアサヒビールの広告には全て「我々の企業姿勢は間違っていない」とする躍進企業ならではの自負、つま り紛れもない“熱い想い”が感じとれる。
しかも本広告は、梶氏の定義するところの(1)「消費者やスティクホルダーとの信頼関係をつくる」ことを狙っているし(2)マーケットシェアとマインド シェアの両方を狙ったと想われる企業姿勢の強烈なアピールがあり(3)今後の展開を予想させるシリーズタイトル(“次のアサヒ”への決意です?)は「長期 にわたって商品が売れつづけるために絶対不可欠な信頼関係をつくるコミュニケーション活動」を意識しているとするに十分なのだ。
ただ、製造現場の人物写真をクローズアップし、海洋深層水など「本生」の商品情報をもとに「人々が感動するうまさ」をストレートに訴求した本広告が、梶氏 が本書であげている一連の広告の事例と表現レベルにおいて違うことは明らかである。つまりこの広告は、氏が自ら定義した“アドバタイジング”の定義に見事 に合致しながら、さらに言えば私が氏の記述から抽出した「熱い想いを伝える」という基準までもクリアしながら、これも私が指摘した氏の本心であるところの “鑑賞するに値する”という広告の基準において恐らく“広告”ではないのである。
逃れられない本書の破綻。
梶氏の広告に対する思い入れと、その思いにも拘わらず露呈するその矛盾については、これまで整理してきた通りである。これらを踏まえ、アドバタイジングと プロモーションの分野を改めて示しながら、梶氏が主張する“アドバタイジング”の境界線、あるいは“プロモーション”に課せられた境界線について述べてみ たい。
私は前項において「セールスプロモーション関連の制作物は、主としてリーフレット・パンフレット・ダイレクトメール・店頭ポスター、最近で言えばホーム ページなどのメディアを対象に作成」と記したが、広告理論ではイベント・展示会の類もセールスプロモーションに入る。つまりセールスプロモーションの分野 はメディアが明らかに(広告業界内の認識として)区別されているのである。そして前述した理由で、これらのメディアには「鑑賞するに値する」表現が入る余 地がないのが一般的である。 一方、通常「広告」と言われる分野のメディアも、テレビ・ラジオCM、新聞・雑誌広告と区別されるが、ここに梶氏の言う「鑑賞するに値する」広告と、明ら かに販売促進を狙った表現レベルの広告が共に入り込んでいる状況が現実にある。
梶氏は結局、広告におけるその表現の混入に異を唱えているわけだ。氏の論理では“販売促進として機能する広告”が存在するのは、「『商品を動かす』役割 を、プロモーションではなくテレビCMに押しつけてしまうことを覚えた」(49ページ)からで、「もしプロモーションが『商品を売る』べく機能してくれた ら、いまの不況は、もっと早く解決したのではないか、とぼくは思う。」(50ページ)という論理になる。つまり“プロモーションに商品を動かす力がないか ら、広告が商品を動かすことばかりやっている”というのが氏の憤っているポイントなのである。
しかし本書は「商品を動かす」役割を持ったテレビCM以外の広告の存在について説明がなされていないし、だいいち単なるプロモーションの改善だけで「いま の不況は、もっと早く解決した」などという論理がいかに現実離れしているかは誰が考えても明らかであろう。したがって、仮に梶氏の“アドバタイジング”の 定義における矛盾にすべて目をつぶったとしても、なお本書は論理的な整合性に大きな欠陥があるのである。
梶氏は、本書211ページで、改めて自らの広告への思いを展開しながらブランドと広告の関係について次のように述べている。「本書でぼくは繰り返し『広告 は商品を売るための情報であってはならない』と書いてきた。わが国の広告はこれまでずーっと、目先の商品を売ることだけに目の色をかえて取り組んできた。 だが、それは広告としては、まったく見当違いの、無駄な努力だった。景気の悪いときはもちろん、景気のいいときは、さらにたくさんの商品を売ることに熱中 して、ブランドを確立する長期的視点に立つことができなかった。 そのために、不況が来たとき、価格訴求も効かなかった。」 近頃流行の「ブランディング」と広告の役割について指摘したこの点について、私は改めて勉強してから論じてみたい。なぜなら、日本人とブランドを考える前 提には、いま生きている日本人の意識あるいは日本人が持つ伝統的な意識をどう捉えるかという壮大な検討課題が待ちかまえているはずだからである。単なる広 告表現、単なるブランド論で語ることは恐らく誤った結論を生むであろう。ただ、ここで私が梶氏に言いたいことは、本欄冒頭で示したように、企業は既にブラ ンドを広告などという枠組みを超えたところで構築し始めているという事実と、仮に「目先の商品を売る」ことが「広告としては、まったく見当違いの、無駄な 努力」であったと仮定しても、本書で氏が展開している論理の矛盾は全く解消されないという事実である。
本書48ページに「ぼくは『セールスプロモーション年鑑』(という名前だったかどうかは忘れた)」という文章が出てくる。この一文に私は、物を書くことを 職業とする人間としての梶氏の姿勢に根底から疑いを持った。私が、本書の記述に対して抱いた疑問をまとめてみようと思い立ったのは、実はこの一文が存在し たからである。ここで言う「セールスプロモーション年鑑」という書籍は私が調べた限りでは存在しない。恐らく「セールスキャンペーン年鑑(株式会社日本 マーケティング研究所刊)」の事ではないかと思うが、梶氏の投げやりな記述からは明確にできない。広告関係の出版物専門の吉田記念図書館で検索した限り 「セールスプロモーション年鑑」の名に近いのは「日経SP年鑑 ’96」しかなく、発行年からみて氏の記述とは矛盾が生まれる。「セールスキャンペーン年 鑑」は同図書館にも’73年から’86年までバックナンバーがあり、時期的にも氏の記述と合致するのである。しかし、私の調べはここまでである。したがっ て私は氏の記述の誤りを指摘したいのではない。私が指摘したいのは、昨今のプロモーションを非難する重要な文章の中で取りあげている署名を曖昧なまま「と いう名前だったかどうかは忘れた」などと罪悪感もなく記述しているその姿勢である。少なくとも私と同じ程度の調べをすれば簡単に書名は特定できたはずだ。 その程度の努力もせずにこのいい加減な記述で済ませ、しかもその書籍を販売するという氏の姿勢は、物を書くという活動に対する安易な認識を物語るのはもち ろん、本書全体の信頼性を著しく貶めるものであること言うまでもない。実に悲しいことである。
私が本欄を書くに至った動機は、梶氏のこの根本的な姿勢への疑問であり、あまりにも多すぎる論理の矛盾と破綻である。「マンスリー広告批評」開始以来、私 が一貫して述べてきた通り、今回の書評も“初めに批判ありき”の文章では決してない。揚げ足を取ってやろうなどという姑息な心を私は持ち合わせていない。 ここでも私の想いは、少なくとも「書く」という仕事を中心に19年間仕事をしてきた経験と、そこから生まれた自らの姿勢に立脚した常識において許せなかっ た。それしかないということだけは申し述べておきたい。
(2002年6月24日)