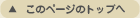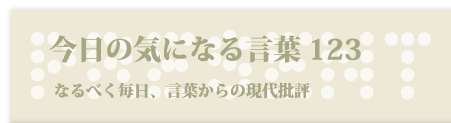
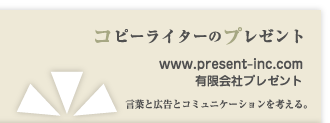
"出きる限り毎日更新"を基本にあらゆるメディアで、
あるいは群衆の中で出合った「気になる言葉」をピックアップ。
すべて123文字で綴った日本語論・日本人論である。 |
★123文字による簡潔な情報伝達の文章スタイルは「知的所有権登録
187441号」を取得しています。 |
10年間にわたるバックナンバーはこちらから |
2007年1月
|
「どちらへ
?」
などと行き先を訊くなんて野暮を江戸っ子は避けたと「朝日新聞」本日夕刊“江戸しぐさ”。プライバシー重視が江戸の住民達の智恵だったのだ。本日、五反田の書店で私が応援する稀勢の里関に遭遇! 激励の一言も伝えたかったけど、言わないのがマナーなのでしょうね。
●No.2111/07.1.31 |
「子供を
産む機械 。」
なる柳沢厚生労働相の失言が大きな波紋を呼んでいる。確かに信じがたい言葉で、思っていなければ出ない表現だ。コメントのしようもないが、小泉議員だったらどう煙にまいたかと考える。私はこの言葉と同等の発言が彼にもあったと思う。そしてその影響は続いている。
●No.2110/07.1.30 |
「お名前を
覚えて ほしい です。」
空前の売り手市場と言われる今年の就職戦線。本日のNHKニュースで学生への取材が行われた。当の女子学生はマイクを向けられた緊張感からこの発言になったのかもしれない。しかし私は、昨今のいびつな丁寧語・謙譲語の氾濫の現れと考える。敬語は、崩壊の一途へ。
●No.2109/07.1.29 |
「会話は
乗客の 皆さんに ご迷惑が かからない ようお願い します。」
というアナウンスは首都圏の電車・バスでは聞かない。しかし長距離電車ではぜひ頼みたいものだと感じた週末の出張旅行。行きの新幹線では母の叱りつける声が、紀勢線では酔客の雑談が、帰りの新幹線でも60代男女の論戦が大声でずっと続いた。マナーの心得、ゼロ。
●No.2108/07.1.28 |
「花粉症の日
。」
ウィキペディアに「花粉症の日」の説明が載っている。花粉が多く飛散する3月上旬の晴れの特異日である3月7日なのだが、「制定」とあるのにどこが制定したのかは不明。日本アレルギー協会に確認したが分からず。どなたかご存じの方は、ぜひご連絡をお待ちします。
●No.2107/07.1.27 |
「教育が
詰め込みで あっても、 かまわない ようなもん だと思うん だがなァ 。」
と橋本治氏(『広告批評』1月)。その通りだ。悪しき“ゆとり教育”の原因の一つに不登校問題があるらしいが、それと学習量を結びつけるのが安易すぎる。改革で10%授業時間を増やすが「それでも米国より少ない」との言い訳も情けなさすぎる。詰め込みこそ教育。
●No.2106/07.1.26 |
「保護者の
利己的 欲求が 持ち 込まれる 。」
全国の学校長の1/3を対象にした東京大学の調査でこんな悩みを持つ割合が78%に上った(本日の『時論公論』)。教育改革で見落とされているのが親の教育である。規範意識が改革の柱の一つに挙げられるが、規範意識のない親をどうするのか。解決は極めて困難だ。
●No.2105/07.1.25 |
「私たちの
行動の 80%は 検索から 始まる 時代に なったの です。」
そう言い放ったgoogle幹部(本日午前深夜の『NHKスペシャル』再)。確かに検索は平日・休日問わず利用するが、インターネット情報は時に使い物にならないほど古く、(人力に比し)表層的でコンサルティング機能に乏しく、公的信憑性を疑うべき情報も多い。
●No.2104/07.1.24 |
「学校
動物 飼育。」
学校での動物飼育の経験が、電車で高齢者に席を譲るなど子供の社会性を育む、とお茶の水女子大調査(本日の『朝日新聞』夕刊)。人への思いやりを示す数値が飼育を続けるほど上昇するらしい。鳥インフルエンザや悪しき潔癖さが学校飼育を阻んだとすれば歪んでいる。
●No.2103/07.1.23 |
「この番組は
フィク ション です。」
とお断りを入れ忘れた、と「発掘!あるある大事典」を皮肉った本日の「朝日新聞」夕刊。しかしテレビのフィクション性はテレビマンユニオンの今野勉氏が 25年前から論じている。私が出演した番組で私が(持論として)発表した企画は、全てテレビ局に作り直された。
●No.2102/07.1.22 |
「京都のある
料理屋。 京都のさる 料理屋。」
上を最も感動した場所、下を最もがっかりした場所の例として挙げたのが春風亭小朝師(『日経マガジン』1月)。いかにも噺家らしい答えだが、古都にもいろいろあるという事。今週末、京都に一泊するのでいま京都通の友人に情報収集している。でも、NO.1は高い!
●No.2101/07.1.21 |
「冬場は
献血者が 減る。」
本日、小田急「本厚木」駅前で83回目の献血を行う。「4時までにA型あと6人」などと叫んでいたのでJTBに行くのを妻に任せ、その間を利用。看護師さんに訊ねると、特に大事故という訳ではないが冬は常時、不足状態なのだとか。献血車内で見る若者は頼もしい。
●No.2100/07.1.20 |
「お笑い
飽和状態 。」
と「朝日新聞」本日朝刊の見出し。「様々な芸風が出尽くした感があり、ブームが少しさめている」とは「爆笑オンエアバトル」の佐橋ディレクター。アイデア枯渇・視聴率重視のテレビ局側が使い捨てた一面もある。私は“ひな壇”スタイルを見ただけで、げんなりする。
●No.2099/07.1.19 |
「川北
紘一。」
映画の「ゴジラ」シリーズの特撮で知られるこの方の名を、本日の「朝日新聞」夕刊「震度7からの伝言」で見た。神戸市にある「人と防災未来センター」の大震災再現特撮ビデオの制作者だ。一昨年私も観たが恐ろしい迫力だった。あの阪神淡路大震災から昨日で12年。
●No.2098/07.1.18 |
「平均
自責。」
とは韓国語で言う野球用語の「防御率」(『朝日新聞』本日夕刊)。韓国はこれまで使われてきた日本の野球用語の直訳を野球発祥地の英語に移し替える作業を進めている。改めて言葉の重さに気付かせてくれる動きだ。「野球」に和製英語が多いのはいかにも日本らしい。
●No.2097/07.1.17 |
「ほわいと
からー えぐぜんぷ しょん。 いわゆる 残業代の 自由化法案 ですが。」
なる政府の言い方を批判した松崎菊也氏(『サンデー毎日』1/28号)。最初から日本語で言え、という訳だ。そう言えば政治家が日本語の間にはさむ英語は何なんだろう。海外の事例を勉強していると取るか、役人の書類に英語が多いのか、いずれにしても伝わり難い。
●No.2096/07.1.16 |
「参加国の
理解。」
拉致問題に「理解」を示さぬ国はないだろう。本日開催された東アジアサミットで当然ながら安倍議員は拉致に触れたが、日本のマスコミはこの問題における日本の過ちを看過する。そもそも平壌宣言締結が最悪だが遺骨問題も対応が拙い。よその国より自国の反省が先だ。
●No.2095/07.1.15 |
「納豆が
品切れする 恐れが あります 。」
地元の生協に行くと納豆売場に1つも納豆がなく、こんな店長挨拶が。経営危機に陥ったことがある店だけに「危ないかもね」なんて話し合っていたら、“納豆品切”現象は各所で起きているらしく糸井重里さんも目撃談を発信。健康情報番組が一因らしいが、何を今さら。
●No.2094/07.1.14 |
「私が代表
だが、私の 団体では ない。」
と事務所費問題で伊吹文科相(本日の『朝日新聞』夕刊)。収支報告書の虚偽申告は明白とか。「これで教育再生が務まるか」と言われるが全くそうだ。この問題はもっと批判されるべきだが、昔より政治家の倫理が問われなくなったのは小泉議員が倫理を無視したからだ。
●No.2093/07.1.13 |
「モチ。」
という名前の牡3歳の競走馬が京都で勝ったらしい(『朝日新聞』本日朝刊)。馬主の小田切さんに言わせると「喜びを分かち合う縁起物」だからとか。“馬名をつけるのが馬主の最大の特権”と言うらしいが、昔は私も夢見ていた。いや、チャンスがあればきっといつか。
●No.2092/07.1.12 |
「不二家
甘かった 。」
と駄洒落を使って不祥事を報じた本日の「朝日新聞」夕刊。でも、これ社長の発言そのままだったんですね。政治家のずさんな経理といい、批判するのは簡単だが、どうしてもこれらを倫理が希薄になっている日本の象徴としか思えない。放置された空き缶と同根のような。
●No.2091/07.1.11 |
「米百俵。」
は前首相の小泉議員が「痛みを分かち合う精神」の例とした新潟・長岡藩の話だが、実際は「『もらった米は次代の若者を教育する資金に』と諭した小林虎三郎の話を通じ将来ビジョンの大切さを教えた」と半藤一利氏(『東商新聞』1/1号)。小泉は誤解を蔓延させた。
●No.2090/07.1.10 |
「汁物なんか
知るものか 。」
「きょうの料理」で“ダジャレ王”の異名をとる後藤繁榮アナにこの年末年始で遭遇。昨日は「だしいらず・和の汁物の基本」がテーマの番組内容に掛けたダジャレで冒頭いきなり出た。この方、癒し系として人気で本も出版されている。確かに、キャラそのものが面白い。
●No.2089/07.1.9 |
「あなたは
いいわ。 趣味も 広いし、 お友達も 大勢だから 。」
本日遅ればせながら江島神社に初詣。この言葉の主は、参道で聞いた(団塊の世代らしき)ご婦人。団塊の世代という言葉を口に話して歩く男性らもいた。昨日のサンプロで高橋三千綱氏は「団塊の世代などとは言わず“僕ら”と言う」と言ったが、その行方には興味あり。
●No.2088/07.1.8 |
「発見した
ものを 止めない 世代。」
と、今年から大量退職が始まる自分たち団塊の世代を表した山本コータロー氏(本日の『サンデープロジェクト』)。ただ多くがゲバ棒(暴力の意のゲバルトに由来する機動隊用の角材)を捨て企業社会に入った。議論好きで自意識が高い独特の世代ではあると思いますが。
●No.2087/07.1.7 |
「雪捨て場
。」
昨夜は「そのべ」(『五反田MAP』参照)で新年会。そこで新潟県柏崎市出身の奈央ちゃんからこの言葉が。除雪車で道路脇に寄せられた雪の集積場らしいが、静岡生まれ神奈川育ちの私には初耳。早速ネットで調べると北海道から東北、北陸まで情報ズラリ。日本広し。
●No.2086/07.1.6 |
「ウルトラ
マンタロー 。」
いま東京のJR目黒駅の拾得定期券を示すボードに定期券の持ち主を表すこの名前が書き込まれている(知人からの生情報)。購入時、いたずら心で打ち込んだ名前らしいが、落としてみれば自分が「ウルトラマンタロー」と証明できるものはない。デジタル社会の笑い話。
●No.2085/07.1.5 |
「矛より
盾。」
と題してPK戦が続出(3回戦までの38%)するサッカー全国高校選手権を評した「日本経済新聞」本日朝刊。指導に関する情報が全国に普及し、カバーリングやラインの構築など教えやすい守備戦術に時間を割くようになったらしい。未だ日本の最高FWは釜本邦茂だ。
●No.2084/07.1.4 |
「フィレン
ツェ 。」
なぜかこの地に関連した番組が多かった新春。2日のNHKハイビジョンは中越典子さんらがウフィッツィ美術館などを紹介し、3日のBSジャパンは奥田瑛二氏が同じ美術館を案内する。そしてNHKではフィレンツェ在住の塩野七生氏の対談。これは何かの偶然なのか。
●No.2083/07.1.3 |
「美。」
元旦広告を眺めると伊勢丹の「一期一会一美」、資生堂の「一瞬も一生も美しく」、パナソニックの「今年、すべての美しさはプラズマから。」、そして講談社の「『美しい国、日本』を裸にします!」まで「美」の文字が4作。多いのか、少ないと言うべきか、安倍さん。
●No.2082/07.1.2 |
「『書く』
から 『打つ』 への 変化。」
「うわさや中傷が行きかうネット社会の言葉は軽くそして危うい」と元旦の「日本経済新聞」朝刊。だから私は(実名とはいえ)ブログでの批判はやめた。コミュニケーションをネットで代替しようとする意識は恐ろしい。もちろん私も“打つ変化”に乗ってしまっている。
●No.2081/07.1.1 |
10年間にわたるバックナンバーはこちらから |